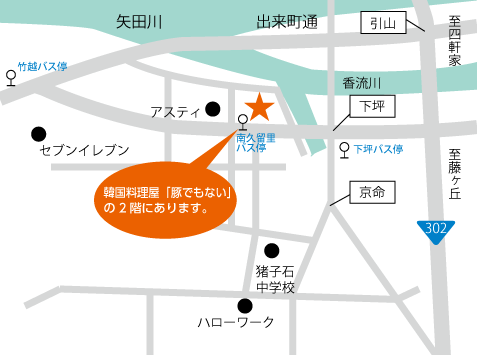【春日井】20代の引きこもりから脱出するには?原因や対処法を解説|不登校|子供の話し方教室

自分の人生を決めていかなければならない10代後半から20代が引きこもりになった時、脱するにはどうしたらよいのでしょうか?
このブログでは、引きこもりの実態や本人の悩みや気持ちを考えていきましょう。
引きこもり・不登校のお子さんをお持ちのご家庭の方のお力になれれば幸いです。
(愛知県・春日井エリアの話し方教室×コミュニケーション講座スタッフが執筆するBlogです)
目次
引きこもりとは?
今現在、引きこもりは社会問題になっています。
仕事や学校に行ってない。最低限の外出しかしない。家族以外の人と交流がない。
厚生労働省は上記の3つを満たした状態を引きこもりと定められています。
引きこもりが長期化すれば不登校や、就職にも影響していきます。
引きこもりになりやすい人の特徴

自分がどこに居ればいいのか、自信を失い後悔して自分を責める気持ちが強い人です。
そして、周りの人との良好な人間関係を築くことができない人に多いようです。
下記に特徴を5つ挙げます。
まじめで頑張り屋
引きこもりは、「怠けている」や「甘えている」というイメージがありますが、真面目でがんばり屋が多いようです。
会社や学校を休むと責任を感じる人が多いようです。
そのため、ストレスが溜まりやすくなり、引きこもりがちになるようです。
自己肯定感が低い
自己肯定感とは、「自分は愛されている」「自分は人に必要とされている」と自分が自分を認められることです。
引きこもりになりやすい人は自己肯定感が低い人が多いようです。
そして、自分に自信がなく、「自分は誰にも必要とされていない」と自分で否定してしまうのです。
内向的な人
引きこもりになりやすい人は内向的で、人と関わるのが苦手な人が多いようです。
ただ、内向的な性格は、生まれ持った性格もあります。
元々一人でいることが好きな人も多いでしょう。
そして、他人と上手く話すことができない人もいるでしょう。
また内向的な人は、自分の気持ちをうまく伝えるのが苦手なため、学校や職場に居づらくなり、引きこもりになるようです。
他人の目を気にする
人目を気にするのは、自分の評価を気にしている事でもあります。
人目を気にする人は自分の言動や才能に自信があるため、もっと上を目指そうとする人が多いようです。
また、自分の思うような評価を得られないと自尊心が傷つき、できない自分に対する不安や怒りを抱くようです。
学校や職場でも人目が気になり、引きこもるようになるようです。
口下手で不満を留めがち
引きこもりになりやすい人は、口下手で、上手く言葉で説明できないため、人間関係がこじれたり、誤解されることが多いようです。
口下手のため、反論できず、心の中に閉じ込めてしまうのです。
また口下手の人は、うまく話すのが苦手だからか、弱音を吐いたり愚痴もあまり言わないようです。
だから、自分の中で気持ちを閉じ込めてしまい、ストレスとなってしまうのです。
周りとの人間関係もうまくできず、気持ちが吐き出せないため、引きこもってしまうようです。
引きこもりの原因は?

引きこもりには様々な要因があります。
統合失調症やうつ病などの精神疾患を患うと、人と会うのが出来にくくなります。
また、育った環境や心が傷ついた体験によって、社会へ出る時の不安で引きこもる場合もあります。
主な原因を下記に7つ挙げます。
親子関係
引きこもりの子供を持つ親には、2つの傾向が見られます。
一つ目が、子供本人の性格や行動に対して愚痴や不満を言ってしまう親です。
だから、自己肯定感の低い子どもに育ってしまいます。
2つ目は、子供にくどくどと説教をする親です。
すぐにダメ出しされたりすると、子供も話をしたくありません。
子供に対して否定的な態度・言動は子供の自信を失わせ、「自分はダメな人間なんだ」と思わせてしまうのです。
人間関係がうまくいかなかった
学生時代のいじめや、職場で仕事ができなかったり、人間関係も崩れたりして、うつ病になることもあります。
入学や就職など、急な環境の変化についていけなくなり、引きこもりになってしまうこともあるようです。
勉強や仕事で挫折した
受験や就活が失敗して、これからどうしていいか分からず、引きこもってしまうこともあるようです。
受験や就活は人生の大きな分岐点だから、余計に人生を悲観して、「もう終わった」などと絶望的になる人もいるようです。
ゲームやインターネットに依存
現実逃避という理由でゲームやインターネットに依存する人も多いです。
ゲームやインターネットは、やり出すとクリアするまでずっとやり続けるため、引きこもりになってしまうようです。
ゲームに熱中して、朝起きられなく、学校や仕事に行けなくなってしまいます。
一日中ゲームし、昼夜逆転し不健康な生活をする人も多いようです。
不登校の延長
いじめや学習の遅れなどから不登校になり、引きこもりになってしまうことも多いようです。
不登校の原因は様々で、子どもの年齢や性格によって異なります。
家庭と学校が協力し不登校の子どもの生活支援や学習支援を進めていくことが良いでしょう。
病気が悪化した
うつ病、不安障害、パニック障害、統合失調症、双極性障害などの病気が悪化したり、外出ができなくなり、人と接することができなくなったりします。
将来に希望が持てなかった
未来に何も希望が持てなくなった、自分にとっての幸せはなんだろうかと思ったり、特別やりたいこともない等生きることを辛いと思ったりと、引きこもりになる場合があるようです。
引きこもりから脱出する対処法

下記に具体的に挙げていきます。
家族の協力
口下手で自分の気持ちを話せない人も、家族になら素直に悩みを打ち明けることができるでしょう。
生活リズムを整える
まず初めに生活リズムを整えることから始めましょう。前向きな気持ちになりやすいからです。
下記を少しづつ実行していきましょう。
早起きする
生活リズムを整えるには、早起きして太陽の光を浴びることで、脳が起きて、活発に動く様になります。
日中に起きていれば、夜は自然と寝れます。それでも夜に寝れなければ、運動などしてみましょう。
外出時の服に着替える
1日中家の中にいると、人目を気にしないから、服も着替えない人が多いです。
メリハリをつける為にも外出できる服に着替えておくと、いつでも外出できます。
そして、定期的に散髪する、毎日お風呂に入るなどして、身なりを整えておきましょう。
1日のうち15分以上は外へ出る
1日中ずっと家の中にいるとメリハリがつきません。
朝起きてすぐ朝日を浴び15分以上散歩に出かけるだけでも、前向きな気持ちになるでしょう。
人とのコミュニケーションを積極的にとる
「近所の人に挨拶をする」といった基本的なコミュニケーションから始めてみましょう。
家族以外の人との接点を増やすことで、徐々にコミュニケーション能力が身に付いていきます。
外部に相談する
第三者に相談することで視野が広がり、自分とは違う考え方や選択肢が新たに見つかることがあります。
医療機関を利用する
病気や障害を患っている人は、医療機関を利用するのもいいでしょう。
家から出るきっかけになったり、専門家によるアドバイスを受けられたり、自分の状態を客観的に見ることができます。
支援団体を利用する
行政施設や医療機関もありますが、他にも自助会、自立支援施設、フリースペースなど、民間の支援団体もあります。
家族ができること

家族は、引きこもりの子どもにとって最も近くて心強い存在です。
引きこもりの子どもが自立できる為にも、家族ができることを下記に挙げていきます。
話を聴く
家族は会話をすることができる唯一の存在です。
食事や団らんなど、話しやすい環境を作ってあげましょう。
話す時は責めたりせずに傾聴し、引きこもりであることを受け入れて認めてあげることが大切です。
子どもと話す時は、尋問にならないような会話を心がけましょう。
子どものためと思って、説得したり励ましたり、子どもの意見に反論したりするのはやめましょう。
子どもに寄り添った会話をしましょう。
お金の話をする
引きこもりの子どもが成人の場合は、将来の事を考えて「働けば、今よりもいい生活ができる」と話してみることも大切です。
ただし話す時は、「働きなさい」などと責めるような言い方はやめましょう。
このように話すと「働かないと生きていけないよ」と伝わってしまい、本人も落ち込んでしまうでしょう。
20代の引きこもりは外部の刺激が必要

引きこもりになって誰とも関わらないと、だんだんと引きこもりからの脱出しずらくなります。
外部からの刺激を受け、視野を拡げるのもいいでしょう。
安心感が得られる
外部からの刺激があると、安心感を得られます。いろんな話を聞いたりしてみましょう。
価値観が広がる
外部からの刺激を受けることによって、価値観が広がります。いろんな人と会っていろんな話をしてみましょう。
まとめ

引きこもりの背景には様々な要因が複雑に絡んでいます。
まず自分で原因を理解し、焦らずゆっくりと対処していくことを考えてみましょう。
そして、自分の力で全て解決しようとせずに、支援施設など色んな力を借りることも大切です。
家族は引きこもり・不登校であることを責めたりせず、本人の意思を尊重して寄り添った会話を意識していきましょう。
家族が引きこもりの子どものケアで疲弊しないよう、適度な息抜きも大切です。
引きこもり・不登校になる人は、元々コミュニケーションで悩んでいることも多いです。
コミュニケーション能力を高める為にも、アトリエシャンティのコミュニケーション講座に通うことをおススメします。
アトリエシャンティは東海・北陸エリアのコミュニケーション講座×話し方教室で、一宮からも多くの方が通われています。
少人数のレッスンで一人一人の課題に合わせ担当講師がしっかりサポートします。
ぜひ、レッスンを体験してみてください。
コミュニケーション講座の体験レッスンは随時募集中です。
岐阜・名古屋・富山で開催中です。
詳しくはこちら
以上、本日の無料公開ブログでした。
お読み頂き誠にありがとうございます!
詳しい情報やノウハウ、技術的な指導や解説は、各教室にて開催されているレッスンにて専門講師陣たちが懇切丁寧にご指導いたします。
当スクールは、少人数で授業を行うため、講師の目も届きやすく、各個人をきめ細やかにサポートし課題を克服できます。そのため、募集定員も各教室20名までとさせて頂いております。
先着順ですので、ご興味のある方はお早めに体験レッスンにお申し込みください。

春日井からのアクセス
春日井からは
お車や公共交通機関でお越しやすい
名古屋千種教室がオススメです。
名古屋千種教室
- 教室外観

外階段を登った2階が教室です - 住所
-
〒464-0004
愛知県名古屋市千種区京命1丁目3-36
シャンティ名古屋ビル 2階
- お車でお越しの方へ
-
近くにコインパーキングあり。
ASTYから徒歩5分。
- 春日井から
-
春日井市役所から
県道30号経由で約25分
- 公共交通機関でお越しの方
-

- 春日井から
-
春日井駅より電車とバス、徒歩で約50分
- JR中央本線 春日井駅より名古屋方面へ
- 大曽根駅で名古屋市営地下鉄 名城線へ乗り換え
- 名城線右回りで茶屋ヶ坂駅を下車
- 名古屋市営バス 茶屋ヶ坂停より猪子石団地行に乗車
- 南久留里停で下車
- 南久留里停より歩いて約2分
- Google Map
-

【春日井】20代の引きこもりから脱出するには?原因や対処法を解説|不登校|子供の話し方教室
当ブログご愛読者様の主要エリア
- 愛知県
-
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村
- 岐阜県
-
岐阜市、大垣市、高山市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、海津市、岐南町、笠松町、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、北方町、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町、白川村
- 三重県
-
津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、志摩市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町
- 富山県
-
富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町
- 石川県
-
金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町
- 福井県
-
福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町
20代・引きこもり・脱出|改善法・解決策|話し方教室|コミュ力UP・コミュ症の克服|岐阜・名古屋・三重・富山・金沢・福井・滋賀|コミュニケーションのコツ教えます|愛知、名古屋、一宮市、春日井市、犬山市、小牧市、豊田市、刈谷市、長久手、津島、東海市、瀬戸市、岡崎市、豊橋市、豊明市、安城市、尾張旭市、岩倉市、江南市、扶桑、清州、愛西市、西尾、蒲郡